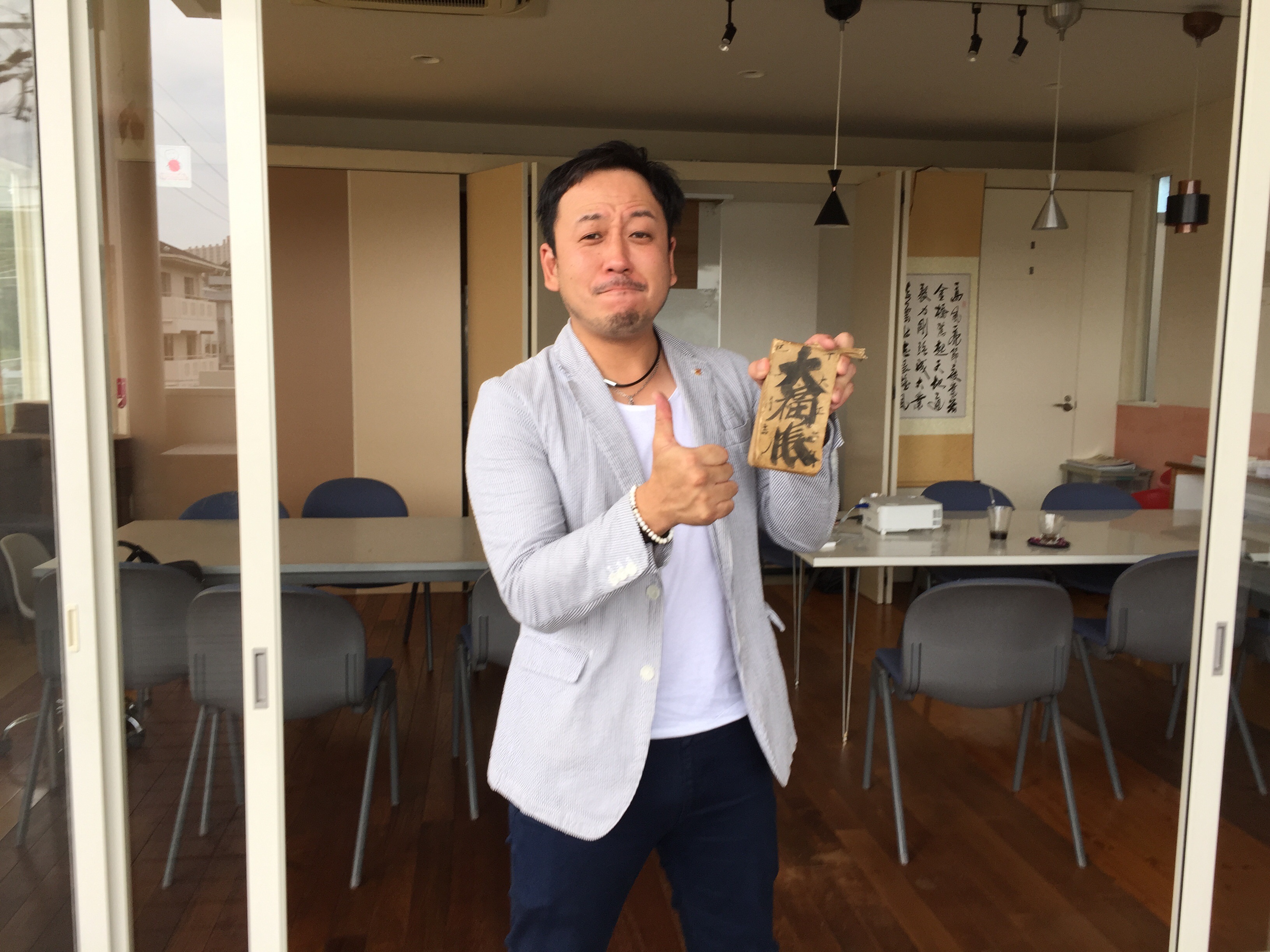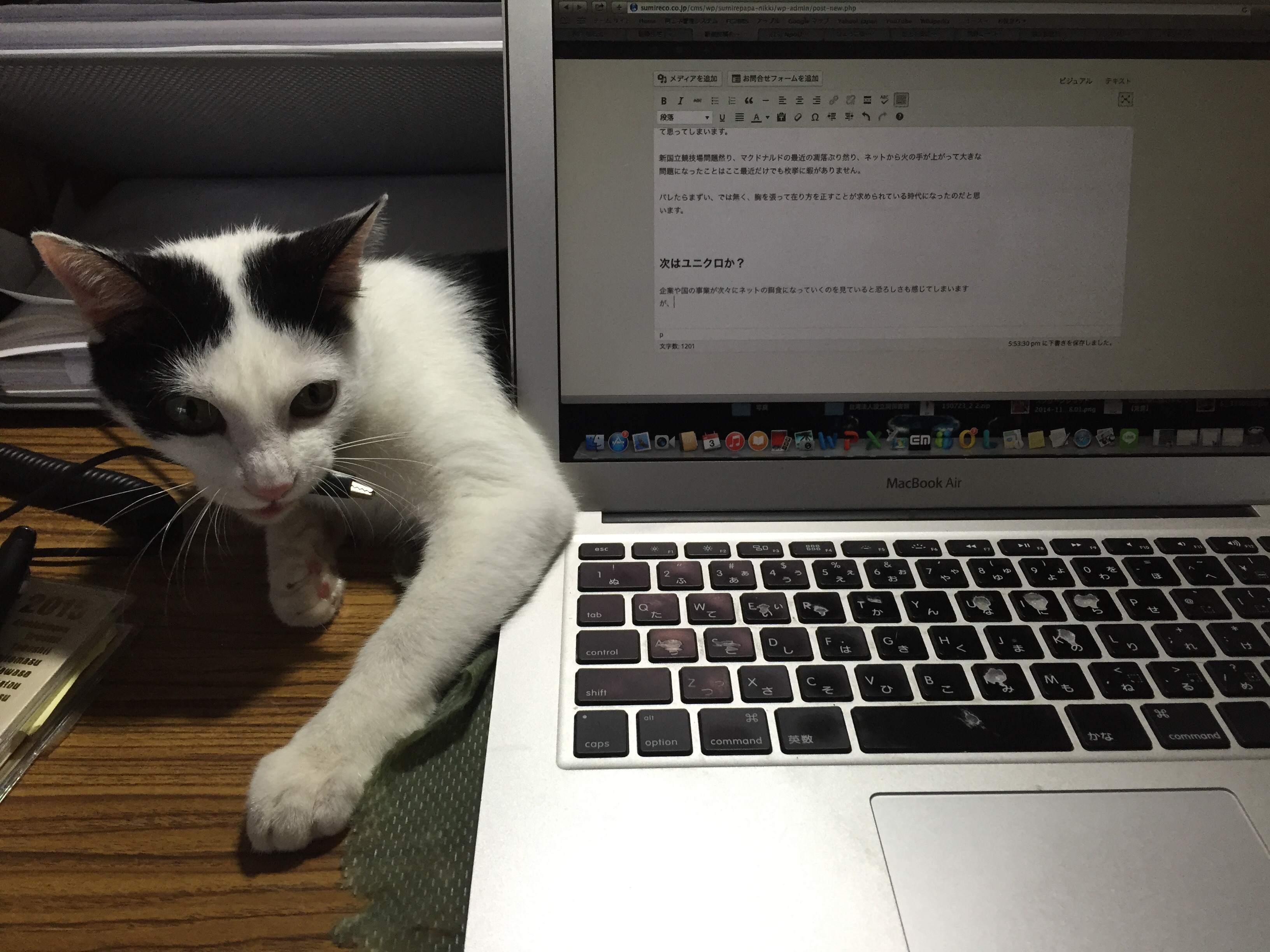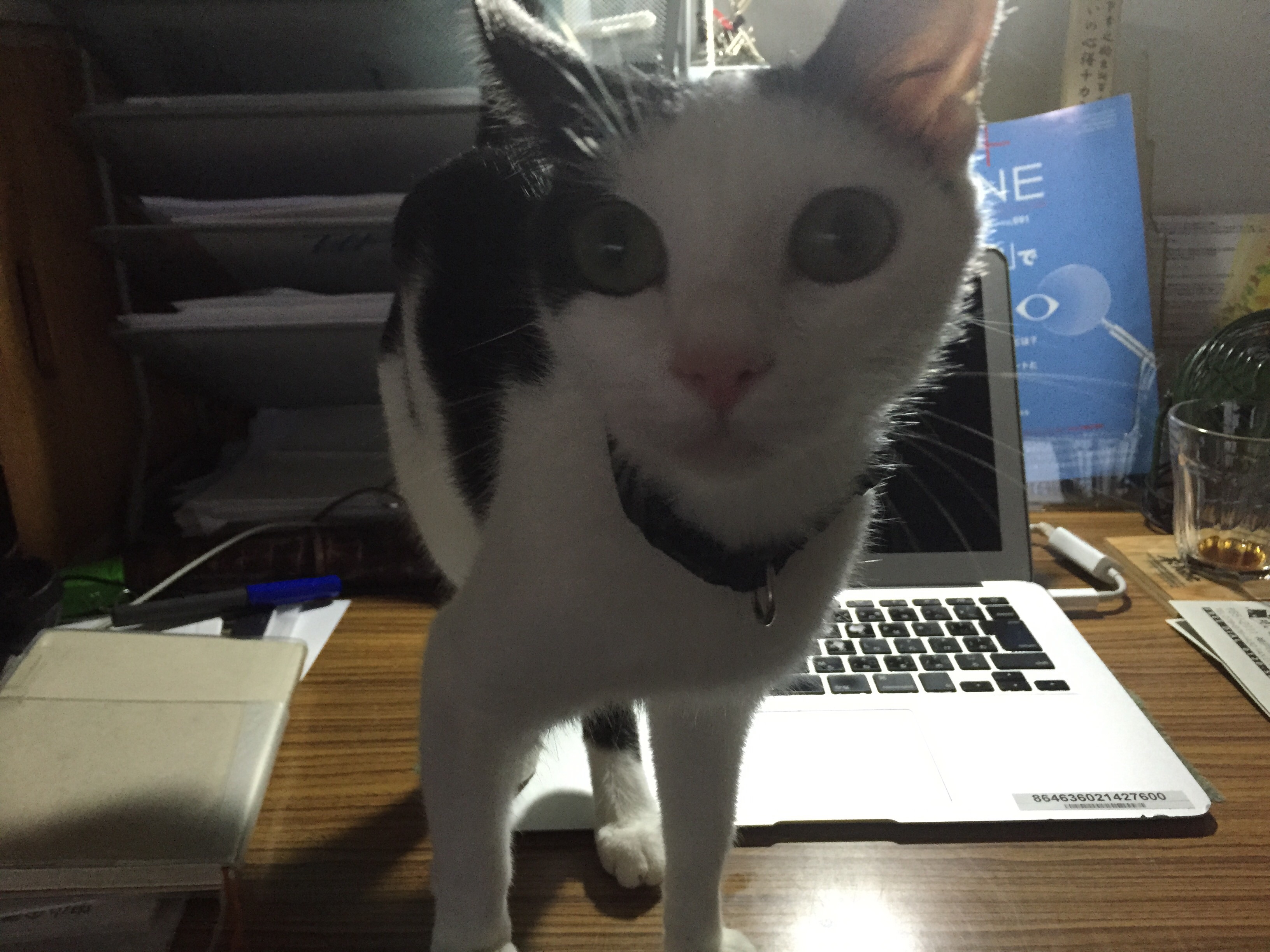9月10日 雨のち曇り

今日は農業研修日
今日は近所の農家さん、『キャルファーム神戸』さんにて農業研修の日。
朝から農作業やる気満々で作業服を着込んで、準備をしていたのに、愛犬チャックの散歩に行くと何故かいつもと違うルートを通りたがり、「しゃあないなー」と付き合ってみたら、やたら熱心にあちこちの臭いを嗅ぎ回り、思いの外時間がかかって帰ってみると、農作業部隊は既に出発。。
置いてけぼりを食らってしまいました。。
でも、これはきっと神様の(ではなく完全にチャックのですが、)思し召しだと思い、掃除とデスクワークに集中する事に頭を切り替えました。
仕事も捗ったし、それはそれで悪く無かったかと。(笑)
ま、収穫してきてくれた野菜は今夜、美味しく頂きたいと思います。

建築会社に不動産の相談。
昼からは顧客からの紹介を受けた、とご連絡を頂いて、「空家になっている家屋をなんとかしたい。」と、ご相談を頂いた方の物件確認へ、丁度雨も上がったのでトレーニングがてら自転車にのって向かいました。一石二鳥とはこの事やなー、なんてすっかりご満悦。上機嫌で雨上がりのアップダウンの激しい住宅街を走り抜けました。
基本的には土地家屋を処分したい、とのご要望なので、(すみれでは不動産免許を取得しておりませんので、)ビジネスパートナーのパワフルなネットワークを駆使して、いいご提案が出来る様に精一杯の努力をしたいと思います。K村社長、宜しくお願いします。
「家の事なら何でもすみれさんに一度相談してみたら、」と、知り合いに奨められたとの事で、全く面識のない方からこの度ご連絡を頂いたのですが、本来、不動産の処分ならその専門業者に相談するのが筋で、そんなことは十分承知の上でのことでした。
ご紹介頂いた方の信頼を裏切らないためにも、ご期待に出来るだけ応えられる様に努力したいと思います。

広告費をかけるくらいなら顧客に使う方がずっとマシ。
それにしても、ご紹介を頂くというのは、本当にありがたいものです。
私たちすみれはマス媒体と言われる、チラシや雑誌、TV、ラジオ等のCMを一切やめてもうすぐ5年になります。とはいえ、毎月新しい工事を受注するには当然、新しくご縁を頂くお客様が必要な訳で、世の工務店さんの殆どが何らかの広告を出して新規顧客の獲得に努めておられます。
会社によって事業の方向性は様々なので、何が正解で何が不正解かは分かりませんが、私たちは規模拡大よりも品質重視、持続継続ビジネスモデルを作り上げることを目指して、創業当初、売上げの3%くらい!も使っていた販売促進費と言われる宣伝広告費をゼロにして、その分をご縁を頂いてお付き合いしている顧客のフォロー、無料巡回メンテナンス訪問を行なって同じお金を使うなら、とそちらに費用をかけることに切り替えました。
現在、全く広告をしなくても毎年同じくらいの売上げを上げる事が出来る様になったのは、その当時から取り組んで来た私たちの姿勢を顧客の皆様が理解して下さったお陰だと思っています。
これからもこのスタンスを貫いて、顧客に生かされている事を真摯に受け止め、スタッフ一同と共に、更なる設計提案、工事品質の向上による『現場顧客満足』を目指して奮闘していきたいと思います。
皆様、引き続き宜しくお願い致します。
一昨日のコーチングセッションにて。
さて、お題目は先日コーチングを受けた際に四辻コーチとの話の中に出て来たコト。
私たちのようなスモールビジネスは、兎にも角にも顧客からの『信頼』を得て、積み重ねる事が何よりも重要です。というか、それ以外に生き残る術は無いくらいに思っています。
その為には、会社、もしくはそこに働く者達の『在り方』を正す事から始めなければならない、それがマーケティンングの根本だと言うのは『7つの習慣』のスティービン・R・コヴィー博士から学んだ事です。
それを日本的な価値観に照らして言い換えると、『魂を磨く』事になるのではないかと思っています。
四辻コーチにはビジネスコーチとしてお付き合い頂いているので、話をする内容は、事業の問題点の解決やスキーム、シクミ作りの話題が殆どです。しかし、我々の共通の認識ではマーケティングの根本は『在り方』を正す事=『魂を磨く』となっているので、魂をどう磨くか、という話題が往々にして登場します。
ハンドクリームの法則
過日もそんな流れから、、
コーチ:「ハンドクリームの話って知ってる」
私:「いえ、知りませんね、聞かせて下さい」
コーチ:「手をスベスベ、ピカピカにする為に、ハンドクリームを使いますよね。」
私:「あ、はい。」
コーチ:「例えば、右の手の甲をきれいにしようと思うと、左の手で塗りますね」
私:「ですよね、」
コーチ:「右の手のひらをきれいにしようと思うと、左の手に塗らないと出来ませんね」
私:「そりゃそうですよね、」
コーチ:「要は、外側をキレイにするには、人に手伝ってもらわないと出来なくて、内側をきれいに磨こうと思うと、人にしてあげないときれいにならないってことですよ。」
私:「あっ、なるほど。」
コーチ:「人間の内なる魂を磨くには、目先の利に囚われず、利他の精神で他人の為に真剣に何かをする事しか無いってことですよね。」
私:「なるほど、分かりやすい例えですねー」
と、こんな話題で盛り上がりました。
マーケティング戦略を立てる、とか、ビジネスモデルをデザインする、とか大げさに聞こえる事も結局、根本はこんなシンプルなのだと改めて感心、納得した次第です。
出来る事なら、すみれのメンバー全員で、右手、左手と言わず、両手で他人様の手にクリームを塗りまくれるような集団になれればいいな、なんて思いました。(笑)
四辻コーチ、いつも示唆に富んだ的確なアドバイス、ありがとうございます!
理解した事をしっかりと行動に移せるよう、この想いを社内で共有する様に致します。
深謝。